武器としての神経症候・高次脳機能障害の診かた 高次は地味だが役に立つ
稲富雄一郎 著
B5判 324頁
定価9,240円(本体8,400円 + 税)
ISBN978-4-498-42826-3
2025年04月発行
在庫あり

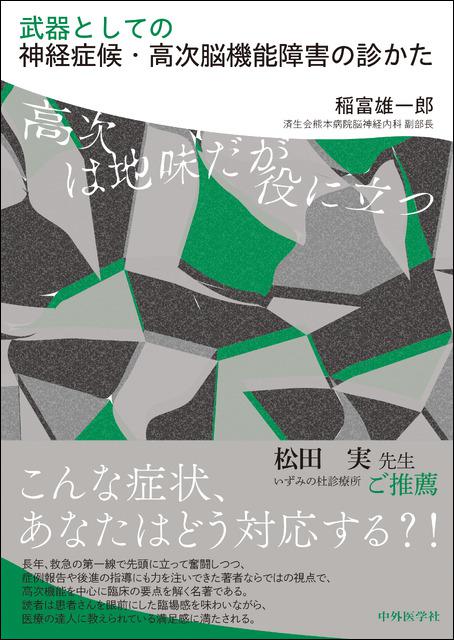
武器としての神経症候・高次脳機能障害の診かた 高次は地味だが役に立つ
稲富雄一郎 著
B5判 324頁
定価9,240円(本体8,400円 + 税)
ISBN978-4-498-42826-3
2025年04月発行
在庫あり
曖昧なことのほうが面白くはないですか?
「高次脳機能・神経心理・神経症候は難しい」を打破するために,診療に臨む著者の頭の中を出来うるかぎり言語化して生まれた本です.そのため,救急や内科外来における時系列に沿ったリアルな症例(第2部:症例編)を軸にしています.しかしながら,症例に臨む前に最低限の準備は必要です.第1部:準備編で適度な理論武装を求めています.症例から診断に迫る過程では,現時点の知識では太刀打ちできない壁にぶつかることと思います.そんなときは,第3部:スキル編(もしくは第4部、第5部)に飛んでください.症例編とスキル編を行ったり来たりすることで,自分の中の知識が日常診療で役立つ武器にまで昇華してくることを想定しています.難解な領域ですが,多くの臨床医にとって,“意外に”役立つ一冊です.
出版社からのコメント
お寄せいただきました書評をご紹介
-----------------------------------------------------------------
長尾病院 高次脳機能センター
田川皓一先生より
本書は神経疾患の救急医療に従事する脳神経内科の専門医による書籍です。通読して、まず思うことは、このような臨床医が身近にいれば、なんと心強いであろうということでしょうか。疾患の予後は、それこそ千差万別です。しかし、自分の症候に対して、これだけ真摯に対応してもらえるのであれば、すべてを託してみたいという気持ちになるのではないかと思います。
本書は救急外来を受診した患者を対象とした臨床経験をもとに、大きく症例編(108例の自験例の紹介)とスキル編(診断や症候学の解説などの総論)に分けて、解説を加えた300ページ以上の大作です。さらに、著者の得意領域である神経心理学領域の諸症状、いわゆる高次脳機能障害を中心とした神経症候学の解説にも多くのページを割いています。救急医療の現場から、神経心理学について、これほど詳述された書籍にお目にかかったことはありません。
著者によると、本書の対象は神経疾患の救急医療に携わる脳神経内科医や救急科の初期研修医から専門医受験前のレジデントとしていますが、その指導医や神経疾患のリハビリテーションに従事する方々にも、是非お勧めしたいものです。医療が急性期病院から、回復期のリハビリテーション病院、さらには維持期の病院や施設へと診療の役割分担が進んでいるなかで、それまでの治療内容が十分に把握できないままリハビリテーションを継続していることも多いのではないでしょうか。受け持ち患者の救急外来における緊張感あふれる医療現場を学ぶことも意味のあることでしょう。
本書を推薦する理由は、著者のこれまでの経歴をよく知っているからです。このような書籍を出版するためには、救急医療に十分な臨床経験があり、神経症候学に豊富な見識を有している必要があると考えます。個人的な話になりますが、著者に初めて会ったのは、まだ彼が医学生の時代でした。卒業後の研修施設を検討するなかで、福岡県飯塚市にある麻生飯塚病院を見学に来た時です。脳卒中の診療や神経心理学に興味を持つ学生が来ているから話を聴いて欲しいとの知人の紹介で、直線距離で20数キロ離れた私が勤務する病院を訪ねていただきました。熱い思いを聴かされたことを覚えています。卒業後、麻生飯塚病院にて研修医として脳神経内科に勤務することになりました。同病院は飯塚市を中心とした地域の中核病院です。脳の血管内手術においては、わが国の最先端の施設でした。そこで神経疾患の救急医療に従事するとともに臨床神経学の基礎を学んだと思います。そのなかで、脳卒中医療や神経心理学への興味がますます鮮烈になってきたようです。そのためには、どうしたらよかろうかと相談を受けたことを覚えています。私は熊本の脳卒中グループに相談することを勧めました。熊本大学脳神経内科が構築した脳卒中の診療体制は、熊本方式として全国に名の通ったものでした。脳卒中の急性期から回復期、維持期にかけての診療体制の構築には素晴らしいものがありました。著者は済生会熊本病院に脳神経内科に勤務することになります。同病院は高度救命救急センターに指定されている熊本における救急医療の中核施設です。両病院を合わせると、30年間以上の臨床経験を積んだのですから、その現場から発せられる言葉には十分な説得力を持っております。
私が脳卒中の急性期の医療現場にいたのは遠い昔のことです。当時を振り返ってみます。まず、脳卒中に似て非なる疾患との鑑別が必要です。この点について著者は豊富な臨床例を紹介しながら解説しています。症例毎に結論や教訓を挙げています。また、そのために参考とすべき要点へと誘導しています。まさに本音で語っているところに説得力があります。脳卒中で出現する神経症候を呈するがゆえに鑑別を要する病態、あるいは、脳卒中に伴って出現する可能性がある自覚症状であるがゆえに鑑別を要する病態、に関する解説には迫力を感じます。次に、脳卒中であれば病型や病巣部位、重症度などの診断が必要になります。最近の治療法や画像診断法の進歩には目を見張るものがあります。今回の脳卒中発作の病態生理の理解ための努力について、症例の紹介が続きます。血栓溶解療法や血栓回収療法の進歩は、時間との戦いでもあります。急性期の臨床現場の緊張を感じることもできます。それぞれの症例で著者の見解を展開しているのは素晴らしいことです。
著者は神経心理学領域の症候、すなわち高次脳機能障害について臨床神経学を志した当初から関心を持っていました。その後、この領域で多くの実績を重ね、神経疾患の救急医療のなかで経験した数多くの臨床例を本書で提示しています。さらに、総論での解説を含め、神経心理学の症候論や局在論、さらには神経心理学的症候の発現機序についての解説を加えており、日常診療に大いに役立つのではないかと思っています。この領域の症候は、要素的な運動障害や感覚障害とは、かなり趣を異にします。患者や家族は何でこのような症候が出現したのか訝ることもよく経験します。このような場合、その症候や発現機序について、考えられないようなとんでもないことが起こったわけではない、奇妙な現象が起こったわけではないことを説明するだけで、気持ちが楽になることもあろうかと思います。その説明の資料になるものではないかと期待できます。
しかし、神経心理学的症候はなかなかの曲者です。臨床の場でよく観察することができる症候もありますが、めったにお目にかかれない症候もあります。同じような病巣があるのに、出現することもあれば、出現しないこともあります。大脳の側性化、大脳優位性なども考慮する必要があります。当然、発現機序については、多くの議論が噴出します。まさに、controversialな世界です。誰かが言い出したらといって、それが正しいというわけでもありませんし、何が正しいか多数決で決めるようものでもありません。用語にしても必ずしも統一されてはいませんし、異なる意味で使用されているかもしれません。個々人の思い入れもあり、自分はこういう用語は使用しないということもあるかと思います。神経心理学はこのような曖昧さを有する領域であることも理解したうえで著者の意見を参考にしたらと思います。この神経心理学領域が有する問題点については、著者自身がよく理解しているようです。本音の部分がQ & Aに語られています。まさに自問自答した著者の考えを知ることができると思います。「相談できる指導者がなく、所見や解釈に自信がありません。どうやって独学したらよいでしょうか?」との質問に対して、研究会や学会での発表、論文の投稿を勧め、院外メンターを作ることの必要性を論じながら、「一番大切なことは批判を恐れないこと」と述べています。本書は、現時点における著者の現在地、到達地点のすべてを、誤解を恐れず開陳した書籍ということができると思っています。私ならば、そうは考えない、そのような解説はしないと思われる所がないわけでもありません。したがって、読者には、本書がすべて正解と短絡的に考えてしまわないで欲しいとも思っています。総論として神経心理学の知識を展開したこれまでの書籍とは趣を異にする本書が、読者が自分なりの解釈を加えることにより、神経心理学領域の関心を、さらにアップデートしていく礎になれば素晴らしいことと思われます。