リーズナブル免疫生物学
吉田龍太郎 著
B5判 224頁
定価5,720円(本体5,200円 + 税)
ISBN978-4-498-10608-6
2019年03月発行
在庫あり

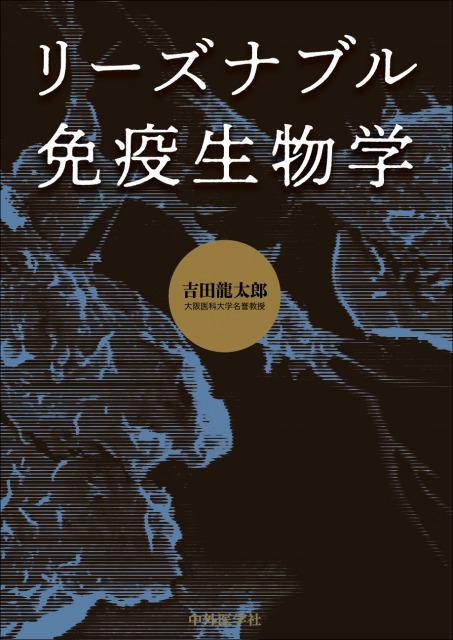
リーズナブル免疫生物学
吉田龍太郎 著
B5判 224頁
定価5,720円(本体5,200円 + 税)
ISBN978-4-498-10608-6
2019年03月発行
在庫あり
“現存する生物は、下等動物であれ、高等動物であれ、それぞれ解剖学的あるいは生理学的には完成品に近い”という著者の考えに基づき、単著でまとめられた免疫学の新たなテキストブック。著者がそう解釈する理由(reason)として多数の論文を引用し、免疫学の全容を初学者にもわかるよう平易に解説した。
まえがき
基礎医学への道
私は,1967年,岐阜大学医学部に入学し,クラブは軟式テニス部に入部しました.新入生歓迎会会場へのバスでたまたま隣り合わせた橋本正彦君が,数日後,軟式テニス部に入部したいので,見学に行くというので同行し,私も試し打ちをさせてもらいました.何度もホームランを打ちましたが,「君,素質あるね.」と褒めまくられ,橋本君と一緒に入部しました.しかし,1年生の冬までは何かに集中するわけでもなく,ブラブラ過ごしました.年が明け,学生時代の半分をクラブで過ごすのなら,頑張ってみようかと,初心者で始めた軟式テニスに打ち込むことにしました.1年生の冬から毎日,早朝のランニングを始め,朝,トーストを食べながら新聞を読み,汗がひくとゆっくり大学に出かけました.私は,典型的な体育会系学生となり,加えて,当時(1968年)学生による東大安田講堂の占拠など学生運動が盛んだったので,教養時代,憲法第9条などの条文と私の解説文を印刷してクラスメートに配布し,学生集会やデモには必ず参加しました.5回生のとき,成田空港用地(三里塚)に行き,約1週間,寝袋・テント暮らしと最寄りの駅での署名活動などにも参加しました.一方,講義は,その分野の専門家がされるのだから,素人が一から勉強するより効率が良かろうと,講義にはできるだけ出席しました.
元々頭脳明晰ではなく,努力もしてこなかったので,卒業後の進路については,内科は無理,子供が好きで手に器用な面はあったので,小児外科医を見指すことにしました.6回生の秋,京都丹波自然公園での近畿医学生軟式テニス大会に出場後,しばらくして,京都大学医学部附属病院小児科の奥田六郎教授に入局希望の件で面会しました.その場で,突然,「今後,生化学が大事だから勉強されては?」と言われました.生化学!? 小児科の医者になる前に大学院博士課程に進み,生化学を勉強して,京大生にない能力を身に付けてから来なさいということだろう.大学院に進学することは,私には卒後の進路としてまったく想定外でした.卒業式後の謝恩会の席上で,軟式テニス部顧問だった福田精耳鼻咽喉科教授から,「吉田が,勉強が好きとは知らなかった.」と言われました.
学生時代の成績がよかったわけではありません.加えて,大学院の試験は,辞書持ち込みなしの英語とドイツ語の2カ国語と一般的知識の3本立てでした.卒業試験を目前に控え,一般的知識は今さらどうにもならないので,私は英語とドイツ語を勉強しました.ドイツ語は教養時代以来でしたから,残っている知識は皆無に等しい.大学院の試験を受けた日は皮膚科の卒業試験の日で,伊藤賀祐教授に事情を説明して,別の日に試験を受けさせてもらいました.当然のことながら,教授のご機嫌はすこぶる悪かった.院生の募集人員に対して定員割れでもしていたのでしょうか,大学院入試に合格し,京都大学医学研究科医化学第一専攻の大学院生になりました.優秀な人がする基礎研究に,私は間違って迷い込んでしまいました.
医化学第一講座の早石修教授は,当時,すでに世界的に有名な生化学者でしたが,私は早石修教授の名前も,勿論,業績も知りませんでした.1973年2月の医師国家試験は,筆記試験と口頭試問からなり,4月25日に合格発表がありましたが,基礎研究に医師免許証は要りません.発行日を私の誕生日にしようと企みましたが,6日遅れの7月19日の発行となりました.
4月1日から京都大学医学部医化学第一講座第4研究部(テーマは緑膿菌のプロトカテキン酸原子酸素添加酵素の構造解析)に大学院生として通学しました.研究のけの字も知らない体育会系学生には何とも難しいテーマでした.直接の上司である野崎光洋助教授から,「これ,読んでおくように」と早石研からの最近の論文の別刷りを数冊手渡されました.英和辞典を引いても載っていない単語が多い.読んでも何のことかわからない.
プロトカテキン酸原子酸素添加酵素は分子量70万の巨大分子で,補因子(鉄)の数やSDS電気泳動でのバンドのパターンから構造が(α2β2)と予想されていました.1年ほどして,たまたま,2種類のサブユニットの分離とN末から14残基のアミノ酸配列の決定に成功しました.野崎助教授から実験結果を論文にするように言われました.英語で論文を書くことは雲の上の話でした.何カ月かかったでしょうか,とにかく,論文の形にして野崎助教授に渡しました.言うまでもありません,最終稿では,私の書いた内容は原型を留めていませんでした.
博士課程後期の私に与えられたテーマは,動物の酵素であるインドールアミン2原子酸素添加酵素(indoleamine 2,3-dioxygenase: IDO)についてで,ベンゼン環とピロール環(インドール環)とアミノ基を持つインドールアミンに基質特異性が広く,酸素源として活性酸素の一つO2−を使うとか,難しい.まして,メチレン青(色素)がIDO活性になぜ必要か? という私のテーマに,私の頭がついて行きませんでした.2年ほど頑張りましたが,大した結果を得られず,「お世話になりました.小児科に行きます.」と言い,早石教授にも奥田小児科教授にも了承されました.しかし,何という運命のいたずらか,小児科に行く直前に,グラム陰性菌の細胞壁の主成分である細菌内毒素(lipopolysaccharide: LPS)によるIDOの誘導を見つけてしまいました.
「君,小児科に行くのかね.」と早石教授に言われ,優柔不断な私は,この世界の怖さを知らず,家内の反対を押し切って研究を続けることにしました.その後,私は5年半医化学第一講座の助手を勤めました.助手時代,早石修教授の名声に集まった院生,佐山重敏,裏出良博,滝川修,渡部紀久子,安井浩明氏らの学位論文の作成に関与しました.1983年,ドイツ,ミュンヘンでの国際トリプトファン研究会議(ISTRY)に参加するついでに,私は,マクロファージを研究している米国ロックフェラー大学のZanvil A. Cohn教授,interferon (IFN)の作用機構を研究している英国の国立医学研究所のIan M. Kerr准教授とプロスタグランディンの研究で1982年にノーベル医学生理学賞を受賞したスウェーデンのカロリンスカ研究所のBengt I. Samelsson教授のところでセミナーをしました.後2者は,IDOの誘導にIFNが関与していることや,そのIFNによるIDOの誘導がプロスタグランディン合成阻害剤で阻害されたからでしたが,従来の研究歴と何の関わりもなかったロックフェラー大学のCohn教授研究室のCarl F. Nathan准教授グループへ客員助教授として留学することにしました.1984年のことです.もう臨床への道はほぼなくなりました.
学問の世界はときに排他的
1962年,ヌード(毛がない)マウスが見つかり,1968年,ヌードマウスにTリンパ球が増殖・分化する胸腺がないことがわかりました.雌のヌード(nu/nu)マウスは,授乳時,乳腺の発達が悪いので,雄のnu/nuマウスと雌のnu/+マウス(胸腺あり)を交配してヌードマウスを増やします(子孫はnu/nu:nu/+=1:1).1971年,ヌード(nu/nu)マウスに他系統の皮膚を移植しても生着しましたが,nu/+マウスの胸腺細胞をヌードマウスに移入すると拒絶されました.そして,1976年,数種類の遺伝子の組換えによって数百万種類の抗体(B cell receptor:BCR)が産生される分子機構が解明され,1984年にはT細胞受容体(T cell receptor:TCR)の構造が解明され,抗体産生機構と類似していることが明らかになりました.素晴らしいメカニズムで,“リンパ球の役割を調べるのが免疫学”と考えられるようになりました.
そんな中,1981年,オーストラリアの有名なIan F. C. McKenzie研究室のBruce E. Lovelandは,1970年代後半に,キラーT細胞とヘルパーT細胞の表面抗原が見つかったのを受けて,adult-thymectomized, X-irradiated, bone marrow-reconstituted(ATXBM)マウスに,どちらのT細胞を移入すると移植拒絶反応が起こるか調べました.非常に素直な実験です.その結果,移植拒絶反応に必要なT細胞は,キラーT細胞ではなく,ヘルパーT細胞であるとJournal of Experimental Medicine(JEM)に報告しました.JEMはロックフェラー大学が出版している,当時(現在も),最も歴史と権威のある免疫学の雑誌です.そして,翌年の1982年に5報のMcKenzieとの共著論文を最後に,1996年,CD4やCD8ノックアウトマウスで,彼の実験結果が基本的には正しかったことが証明されるまでの13年間,Lovelandの名前の入った同種異系移植片拒絶に関する論文はMcKenzie研究室などから出ていません.Tリンパ球だが,キラーTリンパ球ではなくヘルパーTリンパ球だと言っただけです.表面抗原として,厳密さが甘い,Lyt-1とLyt-2,分子に対するモノクローナル抗体を使っていることや,後のCD4やCD8ノックアウトマウスとは違ってATXBMマウスを使ったとはいえ,有名なMcKenzie研究室の仕事でも,おそらく学会などで質問攻めに合い,一研究者がその分野から遠ざかりました.学問の世界は,一度ストーリーができあがると頑固であり,排他的です.
素人の単純な疑問
1987年,私は,大阪市の(財)大阪バイオサイエンス研究所細胞生物学部門部長として帰国し,副部長に伊藤誠二,研究員に根岸学と滝川修,ポストドックに奥亨,安井浩明,州鎌和茂,牛尾由美子,大久保明美と榎本俊樹,共同研究員に京大胸部研の院生,福井基成,と岐阜大学泌尿器科の山本直樹,受託研究員に米田幸生,STA(Science Technology Agency:科学技術庁)フェローとしてValery I. Shevchenko,Martha C. Garcia,Antonio Sanchez-Buenoと劉建文,研究補助員として芦高恵美子,佐藤純子,平田恵子,小笠原陽子,辻淳子,永長久仁子,三輪桂子,川崎美和,若林摩代と八尾治加子が参画し,2つ(吉田および伊藤)の研究グループでスタートしました.
自分でテーマを選べる.私は,元々癌を治したいと医学部に進学しました.ただ,癌は簡単には治らないし,癌はaltered self(同種同系)で,1980年代の研究成果から,癌遺伝子の発現か癌抑制遺伝子の欠損などにより癌化すると考えられていました.が,その後,数10年が経過して,癌特異抗原や癌関連抗原の数は増えましたが,そのほとんどが癌特異的ではありませんでした.したがって,癌を特異的に傷害する細胞,分子やその受容体を探す実験系を組むのは難しい,と私は判断しました.一方,A系統のマウスからB系統マウス(同種異系)への細胞や臓器の移植では,1930年代後半のGorerの一連の仕事で,被認識分子が主要組織適合性抗原複合体(major histocompatibility complex:MHC)と判明しており,レシピエントの免疫担当細胞上の受容体によってドナーのMHCが非自己と識別され拒絶されます.そして,当時,ほとんどの研究者や医療従事者は,“自己/非自己を識別できる細胞はリンパ球”と考えていました.
T細胞は胸腺で増殖・分化し,自己MHCクラス1分子の上に自己ペプチドを提示する細胞と強く反応するTCRを発現するT細胞は除く負の選択(negative selection)と,自己MHCクラス1分子の上に非自己ペプチドを提示する細胞と反応するTCRを発現するT細胞を選別する正の選択(positive selection)が知られています.したがって,CTLは自己MHCクラス1上に非自己ペプチドを提示する細胞を傷害できますが,同種異系細胞(非自己細胞)がそのMHCクラス1分子上に同じ非自己ペプチドを提示しても傷害できません(MHC拘束性).すなわち,自己MHC拘束性T細胞は,異系MHCクラス1分子上の自己あるいは非自己ペプチドを提示する同種異系(非自己)細胞を,非自己と認識も,傷害もできません.また,リンパ球の存在は動物の2%くらいの脊椎動物に限られていますが,同種異系の移植片拒絶は,ホヤなどの原索動物,ヒトデなどの棘皮動物,ミミズなどの環形動物やクラゲ,ヒドラなどの原生動物に近い腔腸動物でも知られています.私は,“生物は,進化をしても,似た分子があれば,同じ機能を別の分子にさせることはない”と考え,下等動物にホモログがある,脊椎動物のどんな細胞あるいは分子が自己/非自己を識別しているのか興味を持ちました.
マクロファージとの出会い
発想は正しかったようですが,いかんせん,学生時代,免疫学を習っていませんし,大学院や助手時代,生化学を学びました.1988年,機器の体裁は整いましたが,まだ閑散とした(財)大阪バイオサイエンス研究所の実験室で,免疫学に素人だった私は,1900年初頭,Lathrop(マウスなどの親子関係をしっかり記録しながら繁殖させた,研究者ではない普通のご婦人.彼女の飼育したマウスなどが世界最大の動物実験施設,米国のJackson研究所,に引き継がれています.)が乳がん細胞をマウスの皮内に移植後,拒絶された実験と,1937年にPeter A. Gorerが被認識分子としてMHCを見つけた実験系を利用することにしました.すなわち,非自己を識別し,傷害するエフェクター細胞を同定するために,C57BL/6マウスにBALB/cマウスで継代した巨大な腹水型線維肉腫細胞,Meth A細胞,を腹腔内に移植しました.まず,論文として通り易いテーマ,IDOが移植片か宿主細胞かどちらで誘導されるか,調べました.その後,経時的に腹腔内からMeth A細胞と浸潤細胞を回収し,低速遠心で移植したMeth A細胞を沈渣として除き,さらに,浸潤細胞を表面抗原に対する蛍光標識抗体で標識し,セルソーターでCD8+,CD4+やMac-1+ 細胞として単離しました.形態,表面抗原や機能(貪食能)などから,自己/非自己を識別し,非自己細胞を傷害するのはリンパ球ではなく,非常識にも,マクロファージである,とProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(米国科学アカデミー紀要)に投稿し,Reviewers(論文を本雑誌に掲載してもよいか審査するその分野のエキスパート)にボロボロに言われながらなんとか掲載されました.私は,米国留学時代に,初めてヒト単球の単離法を習い,coverslipやシャーレ上で分化するマクロファージの培養法を学びましたが,所詮,免疫学には素人でした.その後,自己/非自己を識別し,非自己細胞を傷害するのはリンパ球ではなく,マクロファージである,と続報を書いても相手にしてもらえず,reject(投稿した雑誌から門前払い)される日々が約5年続きました.学会では,多くの日本の免疫学の諸先輩から罵声に近い質問を受けるか,前の演題が終わるとほとんどの聴衆が別の会場に移動されました.そして,実験でも,正常な細胞の代表として用いられてきた非自己リンパ芽球を傷害するのはCTLと判明し,大阪バイオサイエンス研究所の評価会議で研究者としての資質を問われました.10年契約ゆえ,退職まで1年4カ月でした.
実験結果から学ぶ
この1年4カ月がなかったら,私は50歳直前で臨床医に転向したか,別の職業についていたと思います.ただ,不思議なことに,1年4カ月後(1997年6月15日)の退職が決まった途端に,投稿していた懸案の論文がaccept(掲載通知)され,数報の関連論文もacceptされました.大阪バイオサイエンス研究所を退職するまでの1年4カ月間,私は,今までに得た実験結果の意味を吟味し直し,ただ素直に実験の原則に従うことにしました.当時,細胞傷害活性の測定には,51Crが使われ,標識された細胞から遊離した51Cr量より傷害活性を算定しました.従来,標的細胞として,標識可能な(=51Crを取り込む=増殖する)細胞,リンパ芽球,が使われてきました.しかし,移植したのは,リンパ芽球ではなく,皮膚でした.私は,移植した同種異系皮膚から増殖可能なマトリックス細胞など(skin components)を回収し,それらをドナーの脾臓リンパ芽球の代わりに標的細胞として用いることによって,移植片拒絶にマクロファージが関与することを証明しました.
私は,基礎研究向きだったのか,実験をし,考えると楽しかった.10年間の大阪バイオサイエンス研究所での研究を終え,私の就職先で困りました.次の職がなかったのです.そして,私が選んだ道は,たまった実験結果を私の研究者時代の記録として活字にすることでした.私の恩師の一人である大阪医科大学の藤本守学長にお願いし,図書館を利用させてもらい,論文を数編書きました.一方で,京大在籍時代の友人に,臨床医としての雇用の可能性を聞きました.半年間失業しました.ある日,私が例によって大阪医科大学の図書館で論文をまとめているとき,藤本学長が来られ「研究を続けなさい.」と言われました.家内とも相談して,50歳での臨床医への転向を諦めました.京大の友人にもその旨お伝えしました.藤本学長の出身教室(大阪医科大学生理学教室)の後継者である窪田隆裕教授のご厚意で,1997年12月16日,大阪医科大学の生理学教室講師として再出発しました.
大阪医科大学生理学教室では,助教授,講師の先生や大学院生と机を並べ,実験室や共同機器センターなどを見て回りました.当然のことながら,生理学教室には,電気生理の機器はたくさんありましたが,私の研究に必要なものはありませんでした.奥まった部屋に行くと,畳三畳ほどの部屋にクリーンベンチが一台ありました.正直,ほっとしたのを憶えています.本職は生理学教室の講師です.窪田隆裕教授と久保川学助教授(現岩手医科大学教授)から,生理学の講義や実習の指導をするように言われ,鏡山博行医化学教授から生体防御学Iの一部(T細胞受容体)の講義をするようにと言われました.大阪医科大学の教師としての日々は,講義用プリントを作る前に,先生方がどんな講義をされるか聴かせてもらうことから始まりました.
いろいろ慣れるのに,1年かかったでしょうか.少しずつ実験らしきことを始める余裕も出てきました.たまたま,科研費をもらっている研究者名簿を見て,形成外科の上田晃一講師(現形成外科教授)が部屋に来られ,院生を預けたいが可能かと聞かれました.実験をせず,本を読み,講義用プリントを作っている私へのありがたい話に,「大したことはできませんが,ありがとうございます.」と引き受けました.数カ月後の連休明けに来たのは,博士課程甲の申請締め切りまで7カ月という廣田龍一郎氏(現星ヶ丘医療センター形成外科部長)でした.幸い,大阪バイオサイエンス研究所で見つけていた,IFN-γノックアウトマウスでの脱毛の機構について研究をしてもらうことにしました.とんとん拍子に仕事は進み,田嶋定夫形成外科教授のご配慮もあり,甲での学位取得に間に合いました.その後,大阪バイオサイエンス研究所時代,日清食品から受託研究員として来ていた米田幸生氏(現日清食品研究所課長)に研究生として来てもらい,その1年後には,京都大学の本庶佑教授のご厚意で,ちょうど博士課程を終える田代純子氏(現関西医療大学准教授)が助手として赴任しました.窪田教授のご配慮もあり,分子生物学的機器も徐々に揃い,ラボらしくなってきました.
その後,2004年にかけて,移植部への全浸潤細胞からT細胞を除いてもほとんどの皮膚細胞への傷害活性が残ること,全浸潤細胞は,自己皮膚細胞を傷害しないこと,移植部に浸潤するCTLはドナー型リンパ芽球を傷害すること,マクロファージの移植部への浸潤がCTLの浸潤より数日先行することなどを明らかにしました.
私が免疫学に素人だったがゆえに,一時,研究を断念する危機にも瀕しました.しかし,その後も研究の場(大阪医科大学生理学教室に在籍し,形成外科,耳鼻咽喉科,一般消化器外科,眼科,泌尿器科,阪大微研や大阪薬科大学循環病態治療学教室との共同研究)に恵まれ,2006年,移植部に浸潤するマクロファージ上の異系MHCクラス1(H-2DdおよびH-2Kd)に対する受容体 〔monocyte/macrophage MHC receptor 1(MMR1)およびMMR2〕 cDNAの単離,受容体に対する特異的抗体の樹立,2011年,異系MHC クラス1 transgenicマウスや異系MHCに対する受容体KOマウスの樹立に成功し,2013年,異系MHCに対する受容体KOマウスが,異系MHCクラス1 transgenicマウス皮膚を拒絶できないことを明らかにしました.すなわち,マクロファージ上のTCRやBCRとまったく相同性のないMMR1およびMMR2が自己/非自己(同種異系)の識別と非自己の拒絶に必須であることが判明しました.そして,2014年,本庶佑教授のご推薦で,MHC Class I Recognition by Monocyte-/Macrophage-Specific Receptorsという題でAdvances in Immunologyに総説を書かせていただく光栄に浴しました.
一方,2003年頃から,大阪医科大学耳鼻咽喉科および大阪薬科大学循環病態治療学教室との共同研究で,アレルギーに関する実験を始め,アレルゲンだけを1回鼻粘膜下に投与すると,従来,教科書に書かれているアレルゲン特異的IgE抗体ではなく,非特異的(関連抗原特異的)IgEがマクロファージとinterleukin-4(IL-4)依存的に産生され,2回目の皮下投与でアレルゲン特異的IgEが産生されました.2013年3月末で定年退職後,退官前にたまっていた未発表の実験結果〔アレルギーの初期反応は2段階からなり,第1段階(1回めの投与)で誘導された非特異的IgE+small B細胞が,2回目に感作されるアレルゲン特異的IgE+small B細胞を含むとき,第2段階(2回目の投与)で2回目に感作されたアレルゲンに特異的なIgEが産生される〕を論文として投稿したところ,“自己/非自己を識別し,非自己細胞を傷害するのはリンパ球ではなく,マクロファージ”を言い出した1987年と同様に,投稿した数種類の雑誌から門前払いを食らいました.別の論文にする予定の結果を足して,論文を何度も書き直した結果,2017年11月24日,何とかMicrobiology and Immunologyにacceptされました.私(著者)は定年退官しましたので,今後,スギ花粉などの非自己/アレルゲンに対する受容体cDNAがクローニングされ,所属リンパ節での抗原特異的IgE抗体産生機構が明らかになることを期待しています.
一人で書く教科書
多くの本には,多数決で決まったことや,多数の人が納得する内容が書かれています.したがって,最初に見つけた,あるいは,言った人の実験系で,結果が正しければ,執筆者の解釈の方向で教科書的知識になってしまいます.たとえば,1962年にNorman R. Gristによって発見されたヌードマウスは,68年に,胸腺が欠損していることが報告されて以降,医学と生物学の広範な領域において貴重な実験動物として利用されています.そして,i)ヌード(nu/nu)マウスは,他系統のマウスや種を越えたヒトなどからの腫瘍や移植片を拒絶できず,ii)nu/+(胸腺がある)マウスからのT細胞を移入すると拒絶でき,iii)キラーT細胞はドナーの脾臓リンパ芽球を傷害しました.これらの事実から,キラーTリンパ球が,自己/非自己を識別し,傷害しているということになりました.これら3点セットの実験結果は,それぞれ正しいです.しかし,1970年代にCD4+ヘルパーとCD8+キラーの2種類のT細胞subpopulationが発見され,1996年にそれぞれのノックアウトマウスが樹立されると,同種異系マウスの心臓や腎臓などの移植片拒絶に必要なT細胞が,CD8+キラーT細胞ではなく,CD4+ヘルパーT細胞であることが判明しました.その15年前の1981年,ATXBMマウスでのLyt-1とLyt-2に対するモノクローナル抗体を用いたLovelandの実験結果(移植拒絶反応に必要なT細胞は,キラーT細胞ではなく,ヘルパーT細胞である) は,実験的には十分ではなかったかもしれませんが,基本的な考え方は正しかったわけです.さらに,キラーT細胞(CTL)は同種異系リンパ芽球を傷害できますが,同じMHCを発現する上皮系やある種の間質系細胞を傷害できないことが,我々の実験で明らかになりました.しかし,“CTLによる自己/非自己の識別と傷害”が,一度教科書的知識になってしまうと,簡単には修正されず,“同種異系心臓や腎臓などの移植片拒絶に必要なT細胞は,CD8+キラーT細胞ではなく,CD4+ヘルパーT細胞である”は,せいぜいミステリーとして現在も片付けられ,教科書には書かれていません.新しい説を提唱するには,原典を読み,何が教科書的知識かを見極め,その論拠を崩さざるをえません.しかし,それをやると,有名な研究室の研究者ですら,10数年もの長い間,研究の第一線から退かされる可能性があります.
免疫学をはじめ多くの学問は多岐,細部にわたり,かつ専門化しているので,普通,教科書は各専門家が分担執筆されています.しかし,執筆者の学問的背景や基本的考え方が違うと,実験結果の解釈が各専門家で異なることがあり,各章間で論理が混乱しわかりにくいことがあります.まして,免疫学は歴史が浅く,内容が日進月歩で変化しており,また,各章間で内容の重複も生じます.したがって,もし可能なら,一定の基本的な考え方に基づいて,一人の研究者が教科書を書く方がわかり易いと私は思います.
私は,医学部卒業後,約11年間,生化学を学びました.3年間の米国留学中に細胞生物学を学び,やりたかった,癌の原因と治療の研究をするべく,免疫学の種々の実験をし,それらの結果から,今までの免疫学の教科書には,解釈が偏っている部分があることを知りました.1976年から1984年の“リンパ球の役割を調べるのが免疫学である”というものすごい風が吹き荒れる中,私は,免疫学に素人だったがゆえに,“下等動物は,侵入した異物の自己/非自己をその都度識別し,排除するのに対して,高等動物では,リンパ系細胞が,種々の抗原に特異的に結合できるT細胞受容体(TCR)やB細胞受容体(抗体:BCR)で,抗原情報を記憶し,同じ異物の侵入に対しては,より早く,より強く反応できる”と解釈しました.そして,リンパ球上のBCRとTCRで説明される自己/非自己識別機構と傷害機構に疑問を持ちました.
本書の特徴は,“現存する生物は,下等動物であれ,高等動物であれ,それぞれ解剖学的あるいは生理学的には完成品に近い”という私の考え方に基づいて,種々の免疫分子生物学的実験をし,ときに,得られた結果について,従来の教科書的知識とは異なる,解釈をしました.私は,結果を見てあれ!? と思ったときは,再現性を確かめ,別の実験系で確かめ,分子生物学的手法で分子を同定し,さらに,分子をコードする遺伝子をノックアウトしてその分子の機能を確認しました.そして,私は,臨床のいろんな診療科から院生を預かった関係で,がん,ウイルス,自己免疫,移植,アレルギーや皮膚の毛周期など,広範囲の免疫生物学的実験をしてきました.その結果,こういうことかと納得した我々の実験結果を図や表として入れ,こう考えた方がわかり易いと思ったことを,そう解釈する理由(reason)として論文を引用し,できるだけやさしく解説しました(reasonable免疫生物学).自己/非自己の識別は,あらゆる生物にとって,種の保存や生体防御をする上で必須です.この冊子が,農学,理学,薬学,歯学,生命医科学や医学を学ぶ読者にとって,免疫生物学を理解する一助になれば大変嬉しく思います.
目次
まえがき
基礎医学への道
学問の世界はときに排他的
素人の単純な疑問
マクロファージとの出会い
実験結果から学ぶ
一人で書く教科書
1 免疫生物学序論
1-1 からだの基本的構造
1-2 健康の維持
1-3 自己と非自己
1-4 どこで?
1-5 だれが?
1-6 どうした?
1-7 刑事事件にあって生体防御機構では知られていなかったこと
1-8 自然免疫系細胞上のToll-like受容体
1-9 肥満細胞
1-10 なぜ好中球が一番先に炎症部位に行くのか?
1-11 リンパ球の感染症における役割
1-12 免疫グロブリン(抗体)
1-13 限られた数の遺伝子から無数の抗体が産生される機構
2 免疫生物系の構成
2-1 生物は何のために食べるのか?
2-2 微小循環
2-3 血管とリンパ管
2-4 血球細胞の種類と役割
2-5 血球細胞が炎症部位へ浸潤する順序
2-6 常在性マクロファージの役割
2-7 多核白血球の役割
2-8 浸潤性マクロファージの役割
2-9 リンパ球の役割
2-10 単球と肥満細胞の役割
2-11 細胞の性質を調べる方法
2-12 一次反応と二次反応
3 B細胞免疫
3-1 Edward Jenner
3-2 二度なし免疫現象
3-3 遺伝子の組換え
3-4 抗原特異的抗体の産生機構
3-5 抗体の種類
4 T細胞免疫
4-1 T細胞による自己/非自己の識別
4-2 胸腺
4-3 T細胞の正と負の選択
4-4 T細胞受容体(TCR)の構造
4-5 Th1,Th2サイトカイン
4-6 抗原提示細胞とT細胞
4-7 胸腺からリンパ節へ
5 主要組織適合性抗原と移植免疫
5-1 がんは治る
5-2 主要組織適合性抗原の発見
5-3 移植片拒絶
5-4 ヌードマウスの発見
5-5 T細胞が同種異系を識別し,非自己を拒絶する
5-6 キラーT細胞とヘルパーT細胞
5-7 キラーT細胞ではなくヘルパーT細胞が移植片拒絶に必須
5-8 移植片上の被認識分子
5-9 MHCの拘束性
5-10 MHCクラス1やクラス2上の抗原の性状
5-11 下等動物も自己/非自己を識別し傷害
5-12 骨髄移植
5-13 胎児
5-14 母親と代理母
5-15 胎児混入細胞に対する寛容と拒絶
5-16 胎盤の構造
5-17 妊娠での不思議
6 自然免疫
6-1 自然免疫担当細胞
6-2 監視システム
6-3 炎症と免疫に関与する細胞
6-4 炎症・免疫と刑事事件
6-5 血管の透過性の亢進
6-6 白血球の遊走
6-7 病原微生物
6-8 液性免疫と細胞性免疫
6-9 新しいリンパ球とその機能の発見
6-10 リンパ球が炎症・免疫での主役に
6-11 リンパ球による抗原の特異的認識
6-12 マクロファージは非特異的貪食細胞
6-13 自然免疫細胞による炎症・免疫反応
6-14 ウイルス感染に対する生体防御
6-15 マクロファージによる巨大陰性荷電分子やPSの認識
7 マクロファージによる同種異系移植片拒絶
7-1 同種異系細胞の拒絶
7-2 同種異系移植片上のMHCクラス1分子を認識する受容体
7-3 非自己MHCクラス1 transgenicマウスの樹立
7-4 MMR1,MMR2や両者のノックアウトマウスの樹立
8 獲得免疫
8-1 獲得免疫の役割
8-2 Edward Jennerの功績
8-3 ワクチンの必要条件
8-4 抗体の蛋白構造
8-5 抗体遺伝子の構造
8-6 B細胞による抗体の産生
9 腸管での免疫応答
9-1 腸管の組織と機能
9-2 腸内細菌
9-3 腸の構造
10 母体と胎児
10-1 胎児は同種異系
10-2 血液型不適合による胎児の溶血性疾患
10-3 血液型に対する自然抗体
10-4 非自己白血球に対する寛容
10-5 骨髄移植での寛容
11 サイトカイン
11-1 背景
11-2 性状・機能
11-3 種類
11-4 基本的考え方
11-5 火災報知機的サイトカイン
11-6 以前に侵入した異物
11-7 異物の侵入が初回である場合
11-8 エフェクター細胞の活性化
11-9 侵入現場のclean upと再侵入への備え
11-10 サイトカインの意外な作用
11-10-1.毛周期とIFN-γ
11-10-2.マウス毛包におけるメラニン色素形成と血流
11-10-3.創傷治癒におけるサイトカインの役割
11-11 サイトカインレセプター
12 ウイルス感染と免疫
12-1 小さい病原体としてのウイルス
12-2 ウイルスの単離
12-3 ウイルスの可視化
12-4 ウイルスの構造
12-5 ウイルスの増殖
12-6 ウイルスの細胞生物学的応用
12-7 ウイルス感染
12-8 ウイルスに対する生体防御
12-9 ウイルスに対する細胞性免疫
12-10 ワクチンと抗生物質の相違点
12-11 ワクチンの種類
12-12 ワクチンの副作用
12-13 肝炎ウイルス
12-14 ヒトをがんにするウイルス
12-15 がん遺伝子(oncogene)
12-16 ウイルスの応用
13 プリオン
13-1 狂牛病
13-2 プリオン
14 過敏症
14-1 過敏症という名称は正しいか?
14-2 アレルギーの分類
14-2-1.1型アレルギー
14-2-2.2型アレルギー
14-2-3.3型アレルギー
14-2-4.4型アレルギー
14-3 アレルギー発症機構
14-3-1.アレルゲンが初めて体内に侵入したとき
14-3-2.アレルゲン特異的IgE抗体はいつできる?
14-3-3.鼻粘膜下の所属リンパ節はどこか?
14-3-4.アレルゲン非特異的IgE抗体の産生はIL-4依存性か?
14-3-5.所属リンパ節細胞構成の経時的変化
14-3-6.マクロファージとリンパ球がIL-4とIgEを産生
14-3-7.大小2種類の細胞からなるリンパ節細胞
14-3-8.同じ抗原でIgEやIgGを産生する実験系の確立
14-3-9.だれがIgEを作るかIgGを作るかを決めている?
14-3-10.マクロファージがIL-4の産生量を決めている
14-3-11.スギ花粉以外のアレルゲンに対する反応
14-3-12.非特異的IgE+B細胞のIgEは非特異的か?
14-3-13.非特異的IgE+B細胞は,花粉関連アレルゲン特異的IgE+B細胞?
14-3-14.関連アレルゲン特異的IgE+B細胞の誘導と通年性花粉症
14-3-15.アレルゲン特異的IgE+B細胞とアレルゲンで特異的IgEを産生?
14-4 アレルゲン特異的IgE抗体の産生機構
14-4-1.1回目のアレルゲンの侵入
14-4-2.IgMからIgEへのクラススイッチはいつ起こるのか?
14-4-3.1回のアレルゲン投与で特異的IgE抗体が産生されるのか?
14-4-4.アレルギーは,発症と言うよりアレルゲンを排除する生理的反応?
14-4-5.抗原特異的IgA,IgE,IgGやIgM抗体の産生機構
14-4-6.ある英語の教科書に書かれているplasmablastsとは?
14-4-7.B細胞研究者による最近の実験結果の変化
14-5 アレルギーの治療
14-5-1.1型アレルギーの治療
14-5-2.2型アレルギーの治療
14-5-3.3型アレルギーの治療
14-5-4.4型アレルギーの治療
15 がん免疫の基礎と臨床
15-1 がんは自己細胞由来
15-2 悪性腫瘍の種類
15-3 上皮系細胞,間質系細胞と血液細胞
15-4 バリア
15-5 悪性腫瘍の発生機序
15-6 フィラデルフィアクロモゾーム
15-7 がん遺伝子
15-8 がん抑制遺伝子
15-9 腫瘍細胞の性状
15-10 慢性白血病と急性白血病
15-11 白血病の症状
15-12 急性白血病の分類と治療法の世界的統一(FAB分類)
15-13 その他の白血病
15-13-1.Adult T cell leukemia(ATL)
15-13-2.骨髄腫
15-14 悪性リンパ腫
15-15 腫瘍の臨床的問題点
15-15-1.外科的治療
15-15-2.化学療法
15-15-3.放射線療法
15-15-4.免疫療法
15-16 新しい治療法としての免疫療法
15-17 がん征圧への道
15-17-1.がん特異抗原とエフェクター細胞
15-17-2.がん研究の方向
15-17-3.同種同系と同種異系
15-17-4.移植部に浸潤する2種類の細胞傷害性細胞
15-17-5.AIM-1とAIM-2
15-17-6.AIM-2誘導による移植がん細胞の拒絶
15-17-7.H-2d特異的CTLの標的細胞特異性
15-17-8.上皮系細胞と非上皮系細胞に対する傷害機構は同じか?
15-17-9.皮内に移植された腫瘍細胞の増殖と拒絶
15-17-10.皮内で増殖する腫瘍細胞の制御
15-17-11.皮内に移植されたB16細胞と皮膚の免疫組織学的解析
15-17-12.皮内で一旦増殖し拒絶される腫瘍細胞の制御
15-17-13.皮内に移植されたMeth A細胞と皮膚の免疫組織学的解析
15-18 がん征圧への総括
16 自己免疫疾患
16-1 背景
16-2 機序
16-2-1.先行因子
16-2-2.自己免疫反応誘導期
a.中枢性トレランスの破綻
b.末梢性トレランスの破綻
c.ある種の日本人HLAとの相関
d.B細胞のpolyclonalな活性化
e.分子相同性
16-2-3.慢性炎症期
16-2-4.臓器破壊期
16-3 基本的考え方
16-3-1.エフェクター細胞
16-3-2.何が異常?
16-3-3.何が自己/非自己を識別しているか?
16-4 実験的自己免疫性ブドウ膜網膜炎
16-4-1.背景
16-4-2.未処理およびEAUマウスからのmono-dispersed網膜細胞のPercoll密度勾配遠心法による分離
16-4-3.EAUによる網膜破壊の機序(in vivo)
16-4-4.EAUによる網膜破壊の機序(in vitro)
16-4-5.自己免疫疾患制御への総括
17 生活習慣病
文献
あとがき
索引
執筆者一覧
吉田龍太郎 大阪医科大学名誉教授 著
株式会社中外医学社 〒162-0805 東京都新宿区矢来町62 TEL 03-3268-2701/FAX 03-3268-2722
Copyright (C) CHUGAI-IGAKUSHA. All rights reserved.







